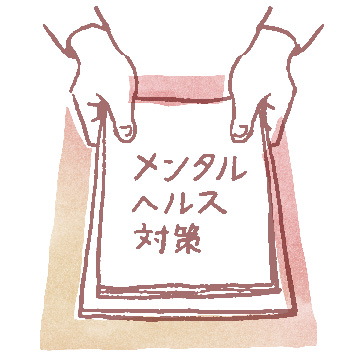
メンタルヘルス対策に関する次のパンフレットもご覧ください。
ストレスチェック制度導入ガイド
Selfcare こころの健康 気づきのヒント集
Relax 職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針〜
Return 改訂心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
1 メンタルヘルス対策に関する施策の経過
職域におけるメンタルヘルス対策に関する国の施策の主な経過は、次のとおりです。
| 年月日 | 施策の内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 昭和60年度(1985) | メンタルヘルスケア研修(昭和60年度にメンタルヘルスケア企画運営委員会設置、講師養成研修会開催。(財)産業医学振興財団。昭和61〜63年度に全国で研修会) | 昭和59年2月の初めての過労自殺労災認定が端緒 |
| 昭和63年(1988) | 労働安全衛生法の改正に基づき「事業場における労働者の健康保持増進のための指針 |
9月1日健康保持増進のための指針公示第1号 |
|
平成7〜11年度 |
労働省の研究班が作業関連疾患(ストレス)について調査研究 | |
| 平成11年(1999)9月 | 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について →平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止 |
9月14日付け基発第544号通達 |
| 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の運用に関しての留意点等について | 9月14日付け事務連絡第9号 | |
| 精神障害に係る自殺の取扱いについて |
9月14日付け基発第545号通達 | |
| 平成12年(2000)8月 | 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針 →平成18年に労働安全衛生法に基づく指針の策定により廃止 |
8月9日付け基発第522号通達 |
| 平成14年(2002)3月 | 職場における自殺の予防と対応(中央労働災害防止協会の委員会、平成22年8月改訂) | 公表資料 |
| 平成16年(2004)1月 | 地域におけるうつ対策検討会報告書 |
|
| 平成16年(2004)8月 | 過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書 | |
| 平成16年(2004)10月 | 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(平成24年7月改訂) →手引中の様式例1〜4(ワードファイル) |
公表資料 |
| 平成16年(2004)12月 | 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」を建議 | |
| 平成17年(2005)11月 | 労働安全衛生法改正(面接指導 |
平成18年4月(50人以上)と平成20年4月(50人未満)施行 |
| 平成18年(2006)3月 | 労働者の心の健康の保持増進のための指針 →平成27年11月に改訂 |
事業場における労働者の健康保持増進のための指針第3号 【パンフレット】 |
| 平成19年(2007)12月 | 労働契約法 |
平成20年3月施行 |
| 平成20年(2008)10月 | 各都道府県にメンタルヘルス対策支援センターを設置→平成26年4月「産業保健活動総合支援事業」に一元化されたことで事業終了 | |
| 平成21年(2009)3月 | 「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」通達 →平成28年4月の通達により廃止 |
|
| 平成21年(2009)4月 | 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の一部改正について →平成23年の「心理的負荷による精神障害の認定基準」により廃止 |
4月6日付け基発第0406001号通達 |
| 平成21年(2009)10月 | 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を開設 | |
| 平成22年(2010)5月 | 労働基準法施行規則の一部を改正する省令にて精神障害が業務上疾病として明記 | 平成22年5月7日厚生労働省令第69号 |
| 平成22年(2010)9月 | 「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ |
|
| 平成22年(2010)12月 | 労働政策審議会が「今後の職場における安全衛生対策について」 |
|
| 平成23年(2011)10月 | 「産業保健への支援の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ |
|
| 平成23年(2011)12月 | 「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出 |
法律案の概要 |
| 平成23年(2011)12月 | 心理的負荷による精神障害の認定基準について →令和5年9月の通達により廃止 |
12月26日付け基発1226第1号 【パンフレット】 |
| 平成24年(2012)1月 | 職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告 |
平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号 |
| 平成24年(2012)3月 | 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ |
【パンフレット】 |
| 平成24年(2012)7月 | 「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の 周知における留意事項について |
7月6日付け基安労発0706第1号
(参考1)質問主意書 (参考2)答弁書 【パンフレット】 |
| 平成24年(2012)9月 | 職場のパワーハラスメント対策の推進について | 平成24年9月10日地発0910第5号・基発0910第3号 |
| 平成25年(2013)6月 | 「産業保健を支援する事業の在り方に関する検討会」報告書の取りまとめ |
|
| 平成25年(2013)12月 | 労働政策審議会が「今後の労働安全衛生対策について」 |
|
| 平成26年(2014)3月 | 「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」を国会に提出 |
●法律案の概要 ●法律案要綱 |
| 平成26年(2014)4月 | これまでの3事業(地域産業保健事業、産業保健推進センター事業、メンタルヘルス対策支援事業)を一元化し「産業保健活動総合支援事業」 |
産業保健総合支援センター、地域窓口(地域産業保健センター)の提供する各種支援サービス(独立行政法人労働者健康福祉機構)
|
| 平成26年(2014)6月 | 「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布 →公布後の「ストレスチェック制度」関連の施策の経過詳細はこちら。 |
平成27年12月施行 ●法律の概要 ●条文 ●新旧対照表 ●通達 |
| 平成27年(2015)4月 | 改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」に関する省令・告示・指針 |
●省令 ●告示 ●指針 |
| 平成27年(2015)11月 | 「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(ストレスチェック指針)」改正 | |
| 平成27年(2015)11月 | 「労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)」改正 | |
| 平成27年(2015)11月 | 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」改正 | |
| 平成27年(2015)11月 | 「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」改正 | |
| 平成28年(2016)4月 | 「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」通達 | 平成28年4月1日基発0401第72号 |
| 平成29年(2017)3月 | 労働安全衛生規則改正(産業医制度の見直し) | 平成29年6月施行 ●新旧対照表 |
| 平成29年(2017)3月 | 「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」通達 | 平成29年3月31日基発0331第78号 |
| 平成30年(2018)7月 | 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」公布(「労働安全衛生法」の改正を含む) |
※労働安全衛生法の改正は平成31年4日1日施行 ●概要 ●法律条文 ●法律新旧対照条文 |
| 平成30年(2018)8月 | 労働安全衛生規則改正(ストレスチェックの実施者に歯科医師・公認心理師を追加) | |
| 平成30年(2018)9月 | 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」公表 | 平成31年4日1日適用 ●報道発表 |
| 令和5年(2023)9月 | 「心理的負荷による精神障害の認定基準について」 |
9月1日付け基発0901第2号 「認定基準改正の概要」 「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書 |
2 メンタルヘルス指針(労働者の心の健康の保持増進のための指針)
近年、労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が6割を超える状況にあります。また、精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にあります。このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっており、事業場においてより積極的に労働者の心の健康の保持増進を図ることは非常に重要な課題となっています。
このため、平成12年8月に策定した「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を見直し、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針として、平成18年3月、新たに「労働者の心の健康の保持増進のための指針![]() 」が策定されました(平成27年11月改正)。
」が策定されました(平成27年11月改正)。
この指針は、次のような内容です。
| 項目 | 区分 | 内 容 |
|---|---|---|
| 衛生委員会での調査審議と「心の健康づくり計画」 | 事業者は、労働者の意見を聴き、産業医など産業保健スタッフ等の助言を得ながら、衛生委員会等において心の健康づくり計画を策定する。 | |
| 4つのケア | セルフケア | 労働者がみずからの心の健康のために行うもの 1 自分のストレスへの気づき 2 ストレスへの対処法の理解と実行 |
| ラインによるケア | 職場の管理監督者が労働者に対して行うもの 1 職場環境等の改善 2 労働者に対する相談対応 |
|
| 事業場内産業保健スタッフによるケア | 事業場内の産業保健スタッフ(産業医、衛生管理者等、保健師等)、心の健康づくり専門スタッフ(精神科・心療内科等の医師、心理職等)、人事労務管理スタッフ等が行うもの 1 セルフケア、ラインによるケアに対する支援の提供(相談対応や職場環境等の改善を含む。) 2 心の健康づくり計画に基づく具体的なメンタルヘルスケア実施の企画立案 3 メンタルヘルスに関する個人情報の取扱い 4 事業場外資源とのネットワークの形成とその窓口となること。 |
|
| 事業場外資源によるケア | 都道府県メンタルヘルス対策支援センター、地域産業保健センター、医療機関他、事業場外でメンタルヘルスケアへの支援を行う機関及び専門家とのネットワークを日頃から形成して活用すること。 | |
| 具体的進め方 | 教育研修・情報提供 |
1 労働者への教育研修・情報提供 |
| 職場環境等の把握と改善 | 1 職場環境等の評価と問題点の把握 2 職場環境等の改善 |
|
| メンタルヘルス不調への気づきと対応 | 1 労働者による自発的な相談とセルフチェック 2 管理監督者、事業場内の産業保健スタッフ等による相談対応 3 労働者の家族による気づきや支援の促進 |
|
| 職場復帰における支援 | 1 職場復帰プログラム(復職の標準的な流れ)の策定 2 職場復帰プログラムの体制や規程の整備 3 職場復帰プログラムの組織的、計画的な実施 4 労働者の個人情報への配慮及び関係者の協力と連携 |
|
表の出典:川上憲人、産業医の職務Q&A第8版、185ページ、2006、(財)産業医学振興財団(一部改変)
3 ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について(通達)
「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について![]() 」(平成28年4月1日付け基発0401第72号)は、労働安全衛生法を改正し、ストレスチェック制度を義務付け、平成27年12月1日から施行されたことを踏まえて、当面のメンタルヘルス対策の進め方を示したもので、その概要は次のとおりです。なお、本通達により、平成21年3月26日付け基発第0326002 号「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」は廃止されました。
」(平成28年4月1日付け基発0401第72号)は、労働安全衛生法を改正し、ストレスチェック制度を義務付け、平成27年12月1日から施行されたことを踏まえて、当面のメンタルヘルス対策の進め方を示したもので、その概要は次のとおりです。なお、本通達により、平成21年3月26日付け基発第0326002 号「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」は廃止されました。
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 労 働 行 政 |
1 事業場に対する周知及び指導の実施等 | (1) あらゆる機会を捉えたストレスチェック制度の周知の実施 (2) ストレスチェック制度に関する指導の実施 (3) 精神障害等による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策の指導の実施 (4) 衛生管理特別指導事業場に対する指導の実施 (5) メンタルヘルス対策のモデル事業場の育成・把握 |
| 2 業界団体等の自主的活動等の促進 | (1) 業界団体等における自主的活動の促進 (2) 啓発活動の促進 |
|
| 3 支援事業の活用等 | (1) 支援事業の活用促進 (2) 産業保健総合支援センターとの連携 |
|
| 4 関係行政機関等との連携 | (1) 関係行政機関との連携 (2) 関係機関との連携 |
|
メンタルヘルス対策については、平成28年4月1日付け基発0401 第72号「ストレスチェック制度の施行を踏まえた当面のメンタルヘルス対策の推進について」(以下「推進通達」という。)に基づき推進していましたが、第4回長時間労働削減推進本部(同年12月26日開催)において「『過労死等ゼロ』緊急対策」(以下「緊急対策」という。)が決定され、メンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策のための取組の強化等を実施することとされました。
これを踏まえ、平成29年1月20日付け基発0120第1号「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(以下「指導公表通達」という。)において、本社管轄署の署長等からの企業幹部等への指導の際には、メンタルヘルス対策(パワーハラスメント対策を含む。)についても指導することとされました。
ついては、メンタルヘルス対策の推進については、推進通達及び指導公表通達に加え、「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について」にもよることと示されています。
※「「過労死等ゼロ」緊急対策を踏まえたメンタルヘルス対策の推進について![]() 」(平成29年3月31日付け基発0331第78号)
」(平成29年3月31日付け基発0331第78号)
4 産業保健総合支援センター
独立行政法人労働者健康安全機構が運営する全国47都道府県の産業保健総合支援センター![]() では、経験豊富な専門スタッフが産業医、衛生管理者、産業看護職、人事労務担当者等の産業保健関係者の皆様に、メンタルヘルス対策をはじめとする産業保健に関する相談、研修、情報提供等の支援を原則として無料で行っているほか、事業主の皆様を対象とした、企業経営の観点から見た産業保健の課題と対策等に関するセミナーや、労働者を対象とした啓発セミナーを開催しています。
では、経験豊富な専門スタッフが産業医、衛生管理者、産業看護職、人事労務担当者等の産業保健関係者の皆様に、メンタルヘルス対策をはじめとする産業保健に関する相談、研修、情報提供等の支援を原則として無料で行っているほか、事業主の皆様を対象とした、企業経営の観点から見た産業保健の課題と対策等に関するセミナーや、労働者を対象とした啓発セミナーを開催しています。
また、地域窓口(通称:地域産業保健センター)![]() では、地域の小規模事業場の事業主や労働者に対して、さまざまな相談への対応、健康診断の事後対応、面接指導等を実施しています。
では、地域の小規模事業場の事業主や労働者に対して、さまざまな相談への対応、健康診断の事後対応、面接指導等を実施しています。
さらに、事業主からの相談内容や要望に応じて、産業保健総合支援センターや地域窓口の専門スタッフが直接事業場を訪問し、メンタルヘルス対策、作業環境管理、作業管理棟状況に即した労働衛生管理の総合的な助言・指導を行っています。
| 項 目 | 事 業 内 容 |
|---|---|
| 1 研修 | 産業保健に関する実践的・専門的な研修 |
| 2 セミナー | 事業場における労働者の健康管理等に関して、事業主、労務担当者及び労働者の理解と協力を促すためのセミナー |
| 3 産業保健スタッフからの相談対応 | 産業保健に関する相談対応 |
| 4 小規模事業場等からの相談対応、個別訪問支援 | 小規模事業場の事業主等への特定健康相談や面接指導への対応 |
| 5 情報の提供 | ホームページ、メールマガジン、情報誌等による産業保健に関する情報提供 |
| 6 調査研究 | 産業保健に関する調査研究 |
5 心とからだの健康づくり(THP)
厚生労働省では、働く人の健康の保持増進を進めるため、 昭和63年からTHP(トータル・ヘルスプロモーション・プラン)を愛称として、働く人の心とからだの健康づくりを推進しています。
THPは、事業者が中心となって、個人の生活習慣を見直し、継続的で計画的な健康づくりをすすめることで、 働く人がより健康になることを目標にしています。具体的なすすめ方については、厚生労働省から指針(令和3年2月改正)が公表されています。
THPをすすめる場合、研修を終了した産業医が健康測定を行い、 その結果に基づき4つの健康指導(運動指導、保健指導、メンタルヘルスケア、栄養指導)等をTHPのスタッフが行います。
THPスタッフをすべて事業場内に揃えるか労働者健康保持増進サービス機関・指導機関を活用する事により、健康づくりが行えます。
THPスタッフの養成のために、中央労働災害防止協会が研修会![]() を開催しています。
を開催しています。
6 衛生委員会
働く人の健康確保をすすめるため、常時働く労働者数が50人以上(派遣労働者・パートタイマー・アルバイト等を含みます。)の事業場では、業種を問わず、衛生委員会を設置して毎月委員会を開催することになっています(労働安全衛生法第18条![]() )。
)。
常時働く労働者数が50人未満の事業場においても、働く人の意見を聴く機会を設けることが必要です(労働安全衛生規則第23条の2![]() )。
)。
衛生委員会については、その構成メンバーや審議する事項などが、次のように決められています。
| 衛生委員会の構成 | 衛生委員会の調査審議事項 |
|---|---|
|
1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 2 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 3 産業医のうちから事業者が指名した者 4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 5 作業環境測定士(事業者が指名した場合) なお、1の委員以外の委員の半数については、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名する。 |
1 労働者の健康障害を防止するための基本的な対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るための基本的な対策に関すること。 3 労働者の健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。 4 その他、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 (1) 衛生に関する規程の作成に関すること。 (2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置で、衛生に関すること(労働安全衛生法第28条の2第1項関係)。 (3) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 (4) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。 (5) 有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること(労働安全衛生法第57条の3第1項、第57条の4第1項関係)。 (6) 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること(労働安全衛生法第65条第1項、第5項関係)。 (7) 法令により定期に行われる健康診断、自発的健康診断及び医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること(労働安全衛生法第66条等、じん肺法関係)。 (8) 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置(THP)の実施計画の作成に関すること。 (9) 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。 (10) メンタルヘルス(心の健康)の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。 (11) 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官、安全専門官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。 |
| 衛生委員会と労働時間等設定改善委員会を兼ねて設置する場合は、上記1を含めた過半数が労働組合又は過半数代表者の推薦によって委員を決める必要がある。(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第6条関係) | |
| 委員会の運営等 | |
|
1 委員会の議長は、上記左欄1の委員がなる。 2 衛生委員会は、毎月1回以上開催する。 3 衛生委員会の開催の都度、遅滞なく、衛生委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させる。 (1) 常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け (2) 書面の労働者への交付 (3) 社内LANその他電子データによる提供 4 衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存する。 |
|
7 職場環境の改善
働く人の心の健康確保のためには、職場環境の改善が効果的です。このため、次により取り組むことが必要です。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 取組みの視点 | 作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労の回復を図るための施設及び設備等、職場生活で必要となる施設及び設備等、労働時間、仕事の量と質、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等の職場内のハラスメントを含む職場の人間関係、職場の組織及び人事労務管理体制、職場の文化や風土等の職場環境等の影響を考慮して、職場レイアウト、作業方法、コミュニケーション、職場組織の改善などを通じた職場環境等の改善に取り組みます。 |
| 職場環境等の評価と問題点の把握 | 管理監督者による日常の職場管理や労働者からの意見聴取の結果を通じ、また、事業場内産業保健スタッフ等(産業医、保健師、衛生管理者等)による職業性ストレス簡易調査票などストレスに関する調査票等を用いた職場環境等の評価結果等を活用して、職場環境等の具体的問題点を把握する。特に、事業場内産業保健スタッフ等が中心になって、職場巡視による観察、労働者及び管理監督者からの聞取り調査、ストレスに関する調査票による調査等により、定期的又は必要に応じて、職場内のストレス要因を把握し、評価する。職場環境等を評価するに当たって、職場環境等に関するチェックリスト等を用いることによって、人間関係、職場組織等を含めた評価を行うことも望ましいものです。 |
| 職場環境の評価や改善のためのチェックリスト等 ・ 仕事のストレス判定図(東京大学大学院医学系研究科(精神保健学・看護学分野)) ・ 職業性ストレス簡易調査票及びその関連マニュアル(東京医科大学衛生学公衆衛生学講座) ・ 職場のソフト面の快適化のすすめ(厚生労働省/中央労働災害防止協会) |
|
| 職場環境等の改善 |
職場環境等の評価結果に基づき、管理監督者に対してその改善を助言するとともに、管理監督者と協力しながらその改善を図り、また、管理監督者は、労働者の労働の状況を日常的に把握し、個々の労働者に過度な長時間労働、過重な疲労、心理的負荷、責任等が生じないようにする等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮を行うことが重要です。 また、その改善の効果を定期的に評価し、効果が不十分な場合には取組方法を見直す等、対策がより効果的なものになるように継続的な取組に努めます。これらの改善を行う際には、必要に応じて、事業場外資源の助言及び支援を求めることが望ましいものです。 なお、職場環境等の改善に当たっては、労働者の意見を踏まえる必要があり、労働者が参加して行う職場環境等の改善手法等を活用することも有効です。 |
出典:メンタルヘルス指針(労働者の心の健康づくりのための指針)
8 面接指導
労働安全衛生法に基づき、医師は、一定の条件を満たす長時間労働者又は高ストレス者に対して面接指導を実施し、その結果を報告書にまとめるとともに、事業者が就業上の措置を適切に講じることができるよう、意見を述べることになっています。
厚生労働省では、医師が面接指導を行う際の参考資料として、マニュアルを公表していますので、具体的な内容は、こちら![]() をご参照ください。
をご参照ください。
9 健康診断
心の健康について調べる健康診断の項目は、法令では定められていませんが、雇入れ時の健康診断、一般定期健康診断(働く人が毎年受けるもの)、特定業務健康診断(深夜業その他一定の有害業務に従事する方が年2回受けるもの)又は海外派遣健康診断(海外派遣前後に受けるもの)を受診すると、問診などもなされますので、これによりメンタルヘルス不調(心の病気やそれに近い状態)があることが分かったときには、会社が医師の意見を聴いて、次により勤務を軽減したり、勤務を休むことが必要になります。また、医師や保健師による医療機関への受診の指導や保健指導が行われることもあります。
| 就業区分 | 就業上の措置の内容 | |
|---|---|---|
| 区分 | 内容 | |
| 通常勤務 | 通常の勤務でよいもの | |
| 就業制限 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じます。 |
| 要休業 | 勤務を休む必要のあるもの | 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じます。 |
出典:健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針![]() (平成27年11月改正)
(平成27年11月改正)
10 職場復帰支援
心の病気で休業していた労働者が職場に復帰する場合には、種々の配慮することがあります。これを円滑にすすめることができるように、厚生労働省が要旨次のような「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(平成24年7月改訂)を示していますので、これを参考としてください。
(1) 職場復帰支援の基本的な考え方
| 職場復帰支援プログラムの策定 |
心の健康問題で休業している労働者が円滑に職場に復帰し、業務が継続できるようにするためには、休業の開始から通常業務への復帰までの流れをあらかじめ明確にしておく必要があります。 事業者は、本手引きを参考にしながら衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受け、個々の事業場の実態に即した形で、職場復帰支援プログラムを以下の要領で策定し、それが組織的かつ計画的に行われるよう積極的に取り組むことが必要です。
|
| 職場復帰支援プラン | 実際の職場復帰支援では、職場復帰支援プログラムに基づき、支援対象となる個々の労働者ごとに具体的な職場復帰支援プランを作成します。その上で、労働者のプライバシーに十分配慮しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、労働者、管理監督者が互いに十分な理解と協力を行うとともに、主治医との連携を図りつつ取り組みます。 |
| 主治医との連携等 |
心の健康問題がどの様な状態であるかの判断は多くの事業場にとって困難であること、心の健康問題を抱えている労働者への対応はケースごとに柔軟に行う必要があることから、主治医との連携が重要です。 また、職場復帰支援においては、職場配置、処遇、労働条件、社内勤務制度、雇用契約等の適切な運用を行う必要がありますので、人事労務管理スタッフが重要な役割を担うことに留意する必要があります(なお、本手引きにおいて、事業場内産業保健スタッフ等には、人事労務管理スタッフが含まれています。)。 |
(2) 職場復帰支援の流れ
| <第1ステップ>病気休業開始及び休業中のケア |
|---|
| ア 病気休業開始時の労働者からの診断書(病気休業診断書)の提出 イ 管理監督者によるケア及び事業場内産業保健スタッフ等によるケア ウ 病気休業期間中の労働者の安心感の醸成のための対応 エ その他 |
![]()
| <第2ステップ>主治医による職場復帰可能の判断 |
|---|
|
ア 労働者からの職場復帰の意思表示と職場復帰可能の判断が記された診断書の提出 |
![]()
| <第3ステップ>職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成 |
|---|
| ア 情報の収集と評価 イ 労働者の職場復帰に対する意思の確認 ウ 産業医等による主治医からの意見収集 (ア)労働者の状態等の評価 (イ)職場環境等の評価 (ウ)その他 エ 職場復帰の可否についての判断 オ 職場復帰支援プランの作成 カ 職場復帰日 キ 管理監督者による就業上の配慮 (ア)人事労務管理上の対応 (イ)産業医等による医学的見地からみた意見 (ウ)フォローアップ (エ)その他 |
![]()
| <第4ステップ>最終的な職場復帰の決定 |
|---|
| ア 労働者の状態の最終確認 イ 就業上の配慮等に関する意見書の作成 ウ 事業者による最終的な職場復帰の決定 エ その他 |
![]()
| 職場復帰 |
![]()
| <第5ステップ>職場復帰後のフォローアップ |
|---|
| ア 疾患の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認 イ 勤務状況及び業務遂行能力の評価 ウ 職場復帰支援プランの実施状況の確認 エ 治療状況の確認 オ 職場復帰支援プランの評価と見直し カ 職場環境等の改善等 キ 管理監督者、同僚等への配慮等 |
11 労災補償
不幸にも仕事によって精神障害にかかったり、自殺された場合には、労災補償制度により一定の補償がなされます。
労災補償を受けるには、病気にかかったご本人、自殺された場合にはご遺族が請求することになります。会社はその手続きを支援することが望まれます。
(1) 労災補償の内容等
| 給付を受けることが できる場合 | 給付の種類 | 給付の内容 |
|---|---|---|
| 医療機関で療養を受けるとき。 | 療養補償給付 | 無料で療養又は全額給付 |
| 傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき。 | 休業補償給付 | 休業1〜3日の間は事業主の支払い 休業4日目以降給付基礎日額の60%給付。別に特別支給金 |
| 療養開始後1年6か月たっても傷病が治ゆしないで障害の程度が傷病等級に該当するとき。 | 傷病補償年金 | 傷病等級 第1級:給付基礎日額の313日分の年金 傷病等級 第2級:給付基礎日額の277日分の年金 傷病等級 第3級:給付基礎日額の245日分の年金 |
| 傷病が治ゆして障害等級に該当する身体障害が残ったとき。 | 障害補償給付 | 障害等級 第1級〜第7級:障害補償年金 (給付基礎日額の313日分〜131日分) 障害等級 第8級〜第14級:障害補償一時金 (給付基礎日額の503日分〜56日分) |
| 障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により現に介護を受けているとき。 | 介護補償給付 | 常時介護:支出額(上限104,950円/月、下限57,030円/月) 随時介護:支出額(上限52,480円/月、下限28,520円/月) |
| 労働者が死亡したとき。 | 遺族補償給付 | 遺族補償年金:給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻は175日分。遺族1人)〜245日分(遺族4人以上) |
| 遺族補償一時金(年金受給資格者がない場合等):給付基礎日額の1,000日分など | ||
| 葬祭料 | 315,000円+給付基礎日額の30日分(この合計額が給付基礎日額の60日分に満たないときは給付基礎日額の60日分) |
(2) 労災認定
労災補償を受けるためには、所轄の労働基準監督署にご本人又はご遺族が請求しますが、その後、その労働基準監督署が仕事との因果関係などを検討するため、種々の調査を行います。事業場関係者、医療機関関係者、ご家族、ご本人などはこの調査に協力をお願いします。
調査の結果に基づいて、専門家の意見を聴くなどにより、次の基準によって、仕事との因果関係などを検討します。
- 「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
 (令和5年9月1日付け基発0901第2号)
(令和5年9月1日付け基発0901第2号)
基準を満たす事例は、業務上疾病として、必要な保険給付がなされます。
12 支援組織
働く人の心の健康確保のために支援する組織、会社がメンタルヘルス対策(心の健康確保)を進めるために様々な支援を行っている組織があります。これらを上手に活用することが望まれます。
| 種類又は団体等 | 支援の主な内容 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専門の相談機関 | 専門の相談機関 | 個々の働く人などの相談の対応 | 無料 | |
| 登録相談機関 | 多くは会社と契約し、従業員の相談の対応 | 会社が経費を負担 | ||
| 精神科・心療内科等の医療機関 | 精神障害等の診断・治療。一部に相談の対応 | 保険診療 | ||
| 独立行政法人 労働者健康安全機構 |
産業保健総合支援センター |
無料 | ||
| 横浜労災病院におけるメール相談(横浜労災病院)、精神科・心療内科のある労災病院における診療 | 無料 | |||
| 中央労働災害防止協会 |
事業場における健康づくり・メンタルヘルス活動に関する各種セミナー、社内研修会の講師派遣、ストレスチェック等、様々なサービスを提供。労災保険の適用事業場であり、常時使用する労働者の数が300人未満の事業場の場合、割引サービスを利用することも可。 | 有料 | ||
| 公益社団法人全国労働衛生団体連合会 |
健康診断と併せて実施できる「全衛連ストレスチェックサービス」を提供しています。 | 有料 | ||
| 公益財団法人産業医学振興財団 |
図書、産業医等研修会 | 有料 | ||
13 自殺対策
自殺対策に関する情報は、厚生労働省の「自殺対策」ページをご覧ください。
関連コンテンツ








